 スカウトに聞かせたいお話
スカウトに聞かせたいお話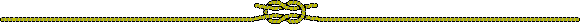
-
◆第11話 パトロールシステム - スカウティングは、「パトロール・システム」によって展開されます。パトロール・システムって、深く考えたことありますか。一人一人の顔が違うように、性格も能力も違います。その、それぞれ違う能力を、グループの中で最大限に発揮し合い、お互いがお互いをささえ合い、助け合ってパトロールのチームワークを最高に作り上げていくことです。
- お経の中に「青色の花には青い光があり、黄色の花には黄色い光があり、赤色の花には赤い光があり、白色の花には白い光がある」と書かれています。つまり、それぞれの持ち味のありったれを発揮して、お互いを照らし合い、他のものを引き立てている世界「相照」の世界こそ「仏の世界」だと述べられています。「仏と国とに誠を尽くす」という、スカウトの「ちかい」を実践してゆく方法こそ「パトロール・システム」だと言えると思います。
- 私たちは、遠い遠い昔から、次々と受け継がれてきた「いのち」を、親を通して恵まれました。また、世界中のたくさんの人やいろいろな物の支えによって、今、生きて、いや「生かされ」ています。お互いにお互いの「いのち」を支え合って生きているのです。
- 人のいのちも、物のいのちも大切に、感謝の心を忘れず、その中で、自分にできる事、自分の一番得意とする事をのばし、奉仕していくこと、それが21世紀の「地球」というパトロールの中でのスカウトだと思うのです。
- お経の中に「青色の花には青い光があり、黄色の花には黄色い光があり、赤色の花には赤い光があり、白色の花には白い光がある」と書かれています。つまり、それぞれの持ち味のありったれを発揮して、お互いを照らし合い、他のものを引き立てている世界「相照」の世界こそ「仏の世界」だと述べられています。「仏と国とに誠を尽くす」という、スカウトの「ちかい」を実践してゆく方法こそ「パトロール・システム」だと言えると思います。
◆第12話 正しく合掌しよう - 仏教でも、キリスト教でも、そのほかのどのような宗教でも、それぞれ合掌とか礼拝という作法があります。
- それは、自分自身の姿勢や動作の上で、その形にととのえて作法することによって、自然にその心がととのえられるからです。
- 「敬いの心ができたら、自然に頭が下がるでしょう」といいうのも道理ですが、身体と心が一体である私たちにとっては「手をあわせて頭をさげることによって、自然に敬いの心がわいてくる」という事もまた事実なのであります。
- 「掌を合わせると真心が目を覚ます」と言われます。背筋を真っ直ぐにして、きちっと合掌すると、心が真っ直ぐに、御仏様や神様の方に向かいます。静かに礼拝すると、そり心は宇山スカウト神仏に対する敬虔な敬いの心に染まってゆくのです。さらに、聖歌を歌い、聖句を朗読し、たとえば「南無阿弥陀仏」あるいは「南無観世音菩薩」と御仏の名を称えると自然にその心に、御仏様が宿ってくださるのです。
- そうして、その御仏様に導かれて、私たちは、人間として、スカウトとして、今日の一日を、あるいは、その一生涯を生きさせていただくのです。
- さあ、背筋を真っ直ぐにして、正しく合掌いたしましょう。
- それは、自分自身の姿勢や動作の上で、その形にととのえて作法することによって、自然にその心がととのえられるからです。
◆第13話 スカウトは親切である - 「おきて」の一つに「親切」があります。親切であるということは、掘り下げて考え、別の言葉に置き換えてみると「奉仕」と言うことです。
- 人にあいさつをするとき、優しい言葉で人に接し、優しいおだやかな表情「顔」で接すると、相手の人は気持ちの良いものです。言葉や表情の表し方ひとつで、人の心をやわらげることができます。親切の第一歩といえましょう。
- 優しい言葉や優しい心が、目や手足の行動に表れて、スカウトの奉仕活動となって、人々にほのかな喜びを覚えさせるものです。
- 親切な言葉と行動が、人を敬い、ひいては仏様を敬う・・・。合掌・礼拝の姿となっていくものです。
- 親切ということは、思いやりの心からでてくる行動といえましょう。曹洞宗の開祖・道元禅師は「愛語は、愛心より生じ、愛心は慈心を種子鳥栖。愛語よく回転の力あることを学すべし」と言っておられます。ここでの愛語とは、優しい言葉ということです。慈心を種子とすとは、慈しみの心、すなわち慈悲深い心をもとにしているという心です。この愛語は人の心の考え方を方向転換させて、喜びと感謝の心に変える働きがあるということを学びなさい。という禅師様の教えでありましょう。
- 私どもスカウトは、いつでも・どこでも・だれにでも優しい笑顔と明るい表情で、人に接したいものです。
- 人にあいさつをするとき、優しい言葉で人に接し、優しいおだやかな表情「顔」で接すると、相手の人は気持ちの良いものです。言葉や表情の表し方ひとつで、人の心をやわらげることができます。親切の第一歩といえましょう。
◆第14話 スカウトは友情にあつい - 満員電車の中に、一人のおばあさんが乗っていました。すると女子高校生がすうっと立って「どうぞ」と言って関を譲りました。その様子を見て、お釈迦様がお説きになった「無財の七施」を思い出しました。
- 無財の七施とは、財なき者にもなし得る、七種の布施行のことです。一らは身施(しんせ)、肉体による奉仕であり、二にし心施(しんせ)、他人や他の存在に対する思いやりの心です。三には眼施(げんせ)、やさしいまなざしであり、そこに居るすべての人の心が和やかになることです。四には和顔悦色施(わげんえつじきせ)、おだやかな笑顔を絶やさないことです。五には言辞施(ごんじせ)、思いやりのこもった暖かい言葉をかけることです。六には床座施(しょうざせ)、自分の席をゆずることです。七には房舎施(ぼうしゃせ)、我が家を一夜の宿に貸すことです。以上が七施で、さきほどの女子高生の行為は、六の床座施にあたります。
- この無財の七施は、日常生活の中で、だれでもできる行為です。一人一人が心がけて、一つでも二つでも実行できれば、優柔が生まれて来て、家庭も社会もなごやかになり、平和な社会、幸福な人生が訪れることでしょう。
- この七施を実践することは、スカウトとしてもっとも大切な奉仕精神を養い、厚い友情を育て、人格形成の一助になるのではないかと思うのです。
- 無財の七施とは、財なき者にもなし得る、七種の布施行のことです。一らは身施(しんせ)、肉体による奉仕であり、二にし心施(しんせ)、他人や他の存在に対する思いやりの心です。三には眼施(げんせ)、やさしいまなざしであり、そこに居るすべての人の心が和やかになることです。四には和顔悦色施(わげんえつじきせ)、おだやかな笑顔を絶やさないことです。五には言辞施(ごんじせ)、思いやりのこもった暖かい言葉をかけることです。六には床座施(しょうざせ)、自分の席をゆずることです。七には房舎施(ぼうしゃせ)、我が家を一夜の宿に貸すことです。以上が七施で、さきほどの女子高生の行為は、六の床座施にあたります。
◆第15話 スカウトは快活である - 私がボーイスカウトを始めた頃、ボーイスカウトのことを早く知りたいと懸命にスカウティング・フォア・ボーイズやその他ベーデン-パウエルの書かれた本を、むさぼるように読んだ者ですが、この「快活」については、スカウトは、どんな困難にぶつかっても、口笛を吹いて、そのことに立ち向かうのだというベーデン-パウエルの言葉が、強烈に私の頭の中に染み込んでいるような気がします。
- 「スカウトは快活である」との実行は、「快活」だけでは実行できないと思います。「おきて」の根本は「誠実」ですが、その他に「友情」も「礼儀」も「親切」も、いや、「おきて」のすべてが実行されて「快活」というスカウトらしさが生まれてくるのだと思います。
- どうも近頃、スカウトたちは「おきて」の実行を忘れているのではないかと思います。号笛の音を聞くことが少なくなったような気がします。以前は、号笛の合図で、機敏に走って集合したものです。敬礼も、いつか知らぬ間に、やることが少なくなって、スカウティング全体が快活さを失った感があります。
- 目立たないようなスカウティングの基本を継承することによって、スカウティングが生き返るのではないでしょうか。
- 集会に集まったとき、敬礼をして、あさのあいさつをする。他団のスカウトと会ったら敬礼を交わす。それこそスカウトらしい仕草だと思うのですが。
- 「スカウトは快活である」との実行は、「快活」だけでは実行できないと思います。「おきて」の根本は「誠実」ですが、その他に「友情」も「礼儀」も「親切」も、いや、「おきて」のすべてが実行されて「快活」というスカウトらしさが生まれてくるのだと思います。
◆第16話 スカウトは勇敢である - 昨年の正月、日本海で、ロシアのタンカーによる重油流出、汚染という事故が発生し、地元の人々の除去作業ではとても手が足りず、広くボランティアの応援が呼びかけれられました。
- また、阪神・淡路大震災の時も、多くのスカウトや指導者がボランティアとして救援に駆けつけ奉仕しました。災害で被害を受けた方達に、救援物資や義捐金を贈ることも必要でありますが、共に汗を流して救援活動をするボランティアも必要です。
- ボランティアという英語は、篤志家、有志、義勇兵、志願兵などと訳されています。この言葉のもとは、VOLOというラテン語で、他から強制されるのではなく、自分の意志で何かを行うという意味です。ですから、「自発活動」が前提条件です。強制や利害関係でやむなく行うのはボランティア活動とは言えません。
- 「おきて」の七は、「勇敢」です。辞書を引くと「勇ましく思い切って行うこと」と出ています。奉仕活動をするには、自発的な強い意志と、まとまった時間が割けること、活動に耐えうる体力、役に立つ技能をもっていること、それにある程度の金銭が必要です。いざとなったら、勇ましく、思い切って自ら申し出で、すぐに行動し、「他の人々をたすける」ボランティアになれるよう、日頃からスカウト活動で十分な訓練をしておくことが望まれます。、
- スカウトは、どんな困難なことがあっても、くじけず、勇敢に乗り越えていってほしいと思います。
- また、阪神・淡路大震災の時も、多くのスカウトや指導者がボランティアとして救援に駆けつけ奉仕しました。災害で被害を受けた方達に、救援物資や義捐金を贈ることも必要でありますが、共に汗を流して救援活動をするボランティアも必要です。
◆第17話 なまこひらきて見きわめよ - B-Pは、スカウト活動の中で、大切なことをいくつも言われていますが、その一つに「観察」をあげています。ボーイスカウトの連盟歌にも「まなこひらきて、みきわめよ・・・」とありますね。
- 私たちは、ふだん、周りのものを自分の「好き」「嫌い」という「ものさし」で見ていることが多いようです。ことに友達関係では、そういうことが多いと思います。「あの人は良い人だ」という時、どこかで「自分に都合のよい人」という気持ちが、「悪い人」と思うとき、「自分にとって都合の悪い人」という気持ちが、どこかで働いていることはないでしょうか。
- 小学校の夏休みにやった「理科」の観察では、私たちにもっともっと広い目で、もっともっと素直な思い出「もの」を見てごらんと教えてくれました。「あ、こんなものもあった。こんな面もあるんだ」と知らされ、知らされることに結って、身近に感じられ、親しみも増してくるのです。
- 仏様は「諦(あきらめ)」つまり「明らかな眼」で物事をみなさいと教えてくださいます。「まなこひらきて、見きわめ・・」たちき、周りの人達の、今まで気づかなかった面も知ることができ、「誰だって、良く知れば、必ず良い所があるんだ」とわかり、もっともっとお互いに手を握り合えるのではないでしょうか。
- 私たちは、ふだん、周りのものを自分の「好き」「嫌い」という「ものさし」で見ていることが多いようです。ことに友達関係では、そういうことが多いと思います。「あの人は良い人だ」という時、どこかで「自分に都合のよい人」という気持ちが、「悪い人」と思うとき、「自分にとって都合の悪い人」という気持ちが、どこかで働いていることはないでしょうか。
◆第18話 キャンプ ありがとう - テントをはり カマドをつくり ごはんを炊き
- そして ハイキングにも出かけた ね
- 楽しかったり つらかったりした キャンプも あしたで終わる
- ふだん ごくあたりまえと思っていることが
- 実は いろんな たくさんな
- 周りの人たちの「おかげ」があったからなのだ と
- 知らされたんじゃないですか
- 一人一人 カオが違うように ひとりひとりココロも違い
- ひとりひとり 得意なこともちがいますよ ね
- そんな中間が集まって それぞれ得意なことを出し合って
- ひとつに まとまること
- それが
- スカウトの「パトロール・システム」って言うことなんです よ
- そんな 人が ものがあって「私」が支えられている
- だから 私もまわりの人たちのために
- 自分のできることをして ささえてあげなくちゃ・・・・
- そういう「勉強」をするのが スカウト活動なんです ね
- ふだん 家では できないこと
- 考えることもなく 過ぎてしまうこと
- そんな
- ごく小さなこと
- でも すごく大切なことを 教えてくれた
- キャンプありがとう!
- そして ハイキングにも出かけた ね
◆第19話 おかげさまといただきます - ふだん、便利なものに囲まれて暮らしていると、忘れていることが多いのですが、自然の中に立つと、自然は私たちにいろいろ大切な事を教えてくれますよ。そうは思っていない人が大半と思うけれど、私たちは、いつも、自分の都合で、まわりを見たり考えたりしています。今朝のような時には、雨はあまり欲しくはありません。すっきりとした青空の下で、快適なキャンプをしたいと思うでしょう?
- でも、まわりの山を見てみましょう。たくさんの木が茂っています。その木々は、この雨に美しく濡れ、とても生き生きと見えませんか? 私たちにとってじゃまな雨も、木や草にとっては、なくてはならない「ごちそう」かもしれません。
- 日本の言葉に「かげ」という言葉があります。「かげ」とは、光のあたらないところ、つまり、よく見えないところのことを言います。
- 私たちは、ふたせん、よく見えるところはよくわかりますが、見えないところについては、考えることもなく過ごしてしまいます。でも、じつは、その見過ごしてしまっている事の中に、とても大切なものが隠れている事が多いのです。
- 昔のことわざら「風か吹くと桶屋がもうかる」というものがあります。説明しますと、昔は今のように道が整備されていなかったし、季節風も強かったので、風が吹くと土埃が舞い上がるのは珍しくありませんでした。それが目にはいる事も多く、こすると目を痛めます。お医者さんも少なく、それが原因で目の病気になり、失明する人も出たわけです。社会保障などは望めませんでしたので、失明した人の中には「ゴゼ」と言って、三味線を弾きながら「門付(かどづけ)」といって、いくらかのお金をもらって、それで生活する人もありました。その三味線をつくるのには、ネコの皮が必要でした。そのためネコが殺されるようになり、ネコを天敵とするネズミが増えました。ネズミはなんでもかじります。そんな事で桶も被害を受け、桶屋さんの仕事が増えて、もうかった・・・・という話です。
- 大分コジツケがありますが、このコトワザは、「世の中、全く関係ないような事が、意外にところでつながっているんだよ」という意味を示すものなのです。
- 天気が悪くガッカリしているスカウトもいると思いますが、天気が悪ければ悪かっただけ、道路事情が悪ければ悪かっただけ、「どうしたら、もっと皆が少しでも来て良かったと思えるようなジャンボリーになるだろう」と、車の運行計画を夜遅くまで考えてくれたスタッフ、朝早く入場してくるスカウトのために、誘導整理の仕事で誰も通らない道にずっと立ってくれたスタッフ・支援の自衛隊の方々・地元の人たちと、数え切れないほどの人々の力があるのですが、多くの人には、その姿はほとんど知られません。
- そのように、ほとんど見えない「かげ」り存在こそ本当は大切なのだという事を、大切なものには「お」を付け、さらに「様」をつけたのが、「おかげさま」という言葉なのです。
- さて、そろそろ朝ご飯の時間です。みんな、ご飯をいただくとき「いただきます」と言いますね。絵、言わない人もいるって? スカウトだったら、みんな残らず「いただきます」と言ってから、ご飯を食べるようにしたいものです。
- どんな宗教でも「いのち」の大切さを教えます。その中でも特に仏教では「いのち」について、それは、人間だけじゃないんですよ。鳥や獣、草や木、更に虫たちだって、同じ大切な「いのち」があるんですよと教えます。
- 私たちが食事をする時、それは、私が今日一日、元気に生活するために、お米や、お魚や、お野菜・・・と、たくさんの「命」をいただいて、私の「いのち」とさせてもらうのだと考えて、目の前に並んだ、たくさんの「いのち」を感謝して「いただく」というココロを表す、それが「いただきます」という言葉なのです。
- だから、心を込めて、はっきりと「いただきます」が言えるスカウトになろうではありませんか。
- さあ、今朝は、どんなごちそうですか? 作ってくれた炊事当番と、それにもまして私たちに捧げてくれた、たくさんの「いのち」に向かって、心から言いましょうね。「いただきます」と。
- 【12NJ FMクマゲラステーション「ラジオ・スカウツオゥン」8月3日 宗教部・相馬順敬さんのことばより】
- でも、まわりの山を見てみましょう。たくさんの木が茂っています。その木々は、この雨に美しく濡れ、とても生き生きと見えませんか? 私たちにとってじゃまな雨も、木や草にとっては、なくてはならない「ごちそう」かもしれません。
◆第20話 「ぞうさん」の贈り物 - まど・みちおさんに会った。童謡「ぞうさん」の作詞家で知られる。
- ぞうさん ぞうさん
- おはなが ながいのね
- そうよ
- かあさんも ながいのよ
- 大人も子供も知らない人はないだろう。象の子供と母親の仲良しこよしの歌だと思っていた。
- 「そうではないのです。象の子が、鼻が長いとけなされている歌なのです。」
- それでも、象の子は、しょげたりしない。むしろ、ほめられたかのように、一番好きな母さんも長いと、いばって答える。
- 「それは、象が「象」に生まれたことは、すばらしいとおもっているからです。」
- 象に限らない。ウサギもイワシもスズメも草や木も、地球に住む生き物たちすべてが、自分であることを喜んでいる。人間だってその中の一員である。これが、まどさんの「ぞうさん」哲学なのだ。
- アイデンティティーとか「自分探し」といって、自分の存在証明に躍起になることもない。「あるがまま」でいいのだ、と言っているように思える。
- 人間も他の生き物も、それぞれに違いがあるからこそ意味がある。その違いを活かして助け合うことが、最前のみち。みんながみんな、心ゆくまでに存在していい。「共生」の考え方だ。
- まどさんは、相手の傷や痛みを自分で引き受けてしまう。そんな詩を読むと、何か途方もなく大切な事をなおざりにしたままでいることに気づかせてくれる。
- 八十八歳。戦前、台湾にいた十九歳から童謡や詩を書く。その数は千を超える。今も書き続ける。
- まどさんは、繰り返し蚊の詩を書く。
- 刺しに来る蚊。思わずたたいてしまうのだが、刺される側のまどさんは、血をすわなければ生きていけない蚊の身の上にまで心を痛める。
- きえいりそうに よってくる
- きんいろの こえを
- 大げさに たたいたあとになって
- ふと おもうことだってある
- むかしむかしの
- りょうかんさんだったらばなぁ・・・・と
- たたいてしまった自分に傷つき、蚊のことが気に掛かってしまうのだ。
- 子供がしゃべった言葉を詩にした作品で、まどさんの印象に残ったのは、教室でトイレに行きたいが紙がなく地団駄を踏んでいる。それを見た他の子供が一緒に足を踏みならしたというものだった。
- 童謡「サッちゃん」の作詞家で、まどさんの評伝を書いた阪田寛夫さんは「私たちが普段見過ごしている小さな、それ故に大事な事を教えてくれます。今でも、新しい発見に向けて、散歩しています。」
- ほかの誰でもない自分が、ほかのどこでもない「ここ」にいる。そのことこそが、すばらしいのだと「ぼくが、ここに」という詩でまどさんは歌う。
- 【H10.6.1 朝日新聞社説より】
- ぞうさん ぞうさん
- スカウティングは、「パトロール・システム」によって展開されます。パトロール・システムって、深く考えたことありますか。一人一人の顔が違うように、性格も能力も違います。その、それぞれ違う能力を、グループの中で最大限に発揮し合い、お互いがお互いをささえ合い、助け合ってパトロールのチームワークを最高に作り上げていくことです。